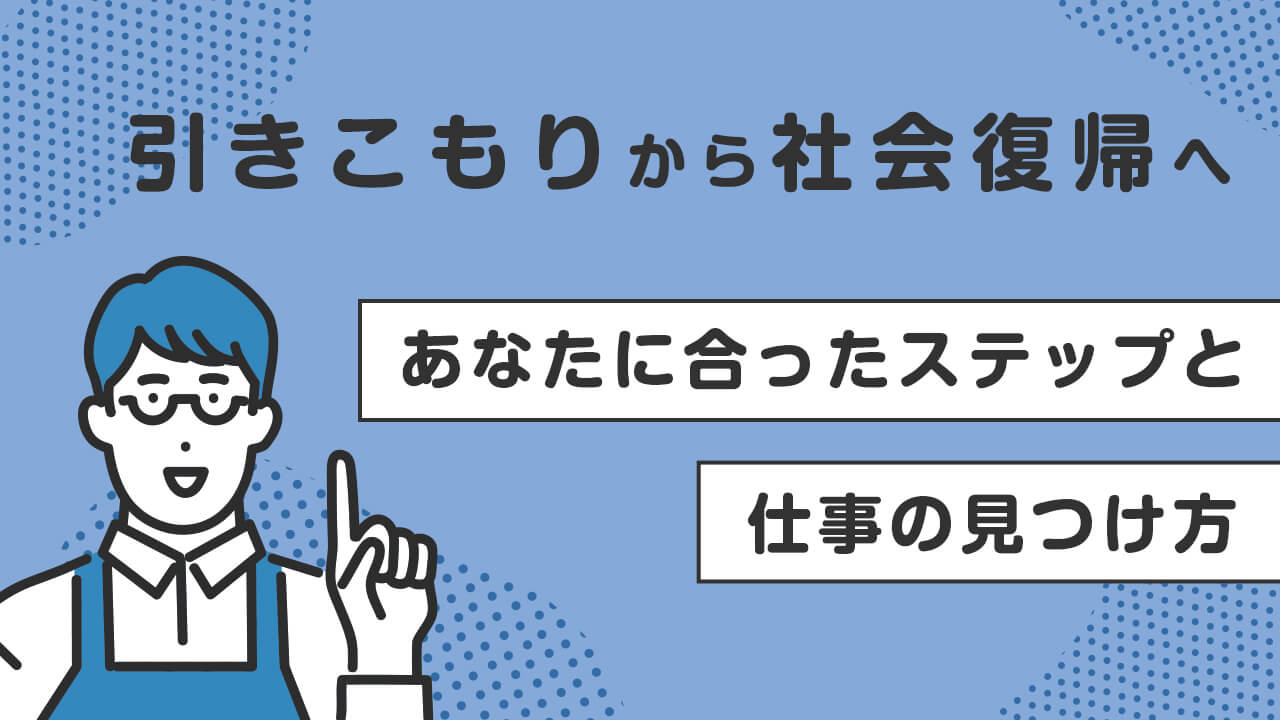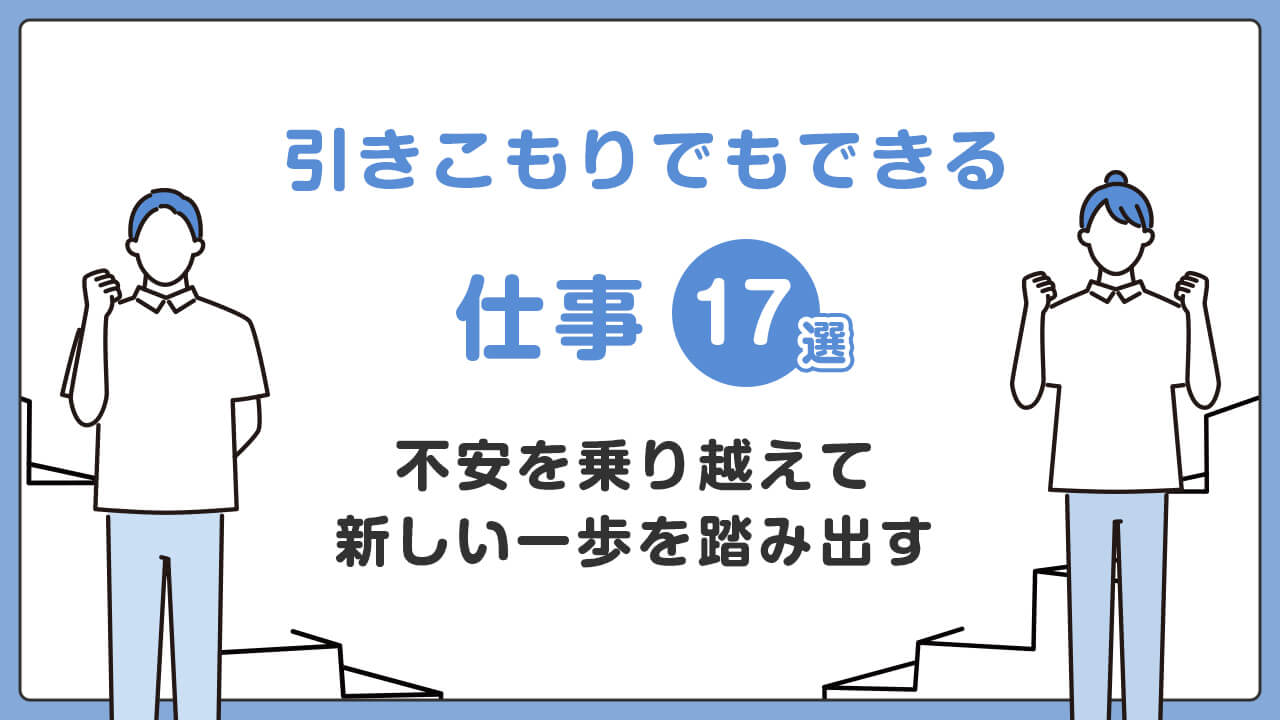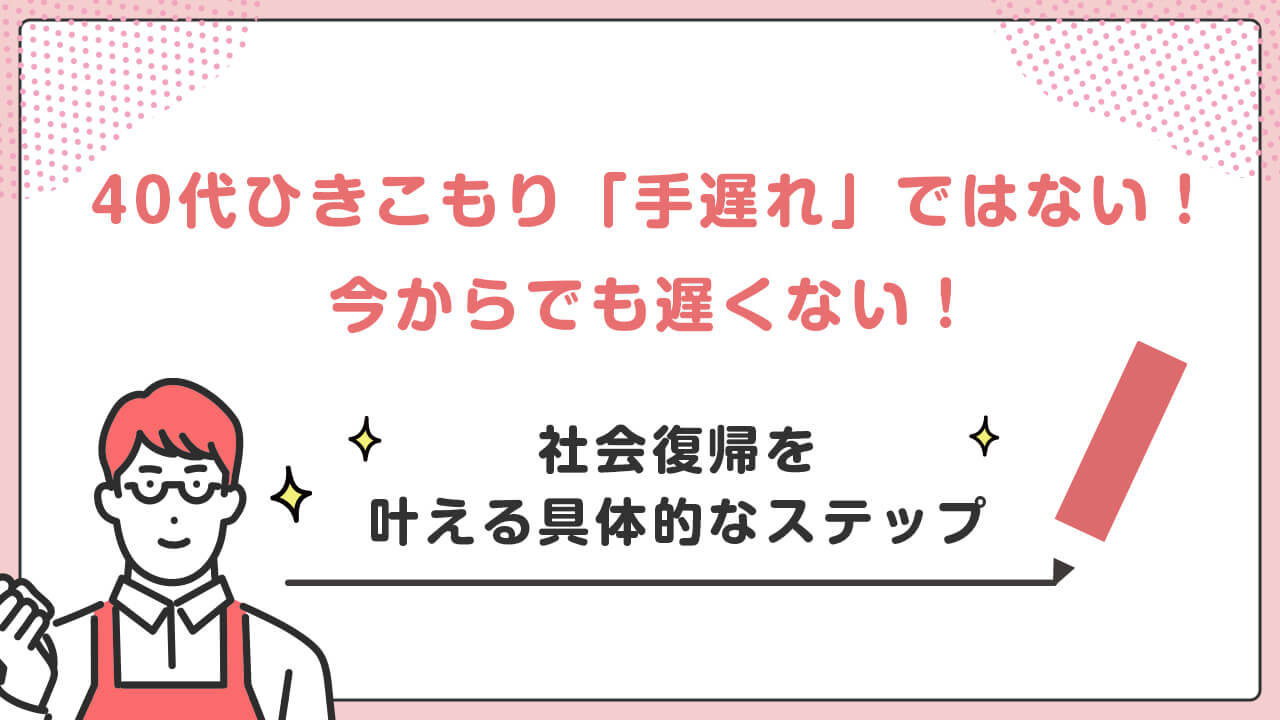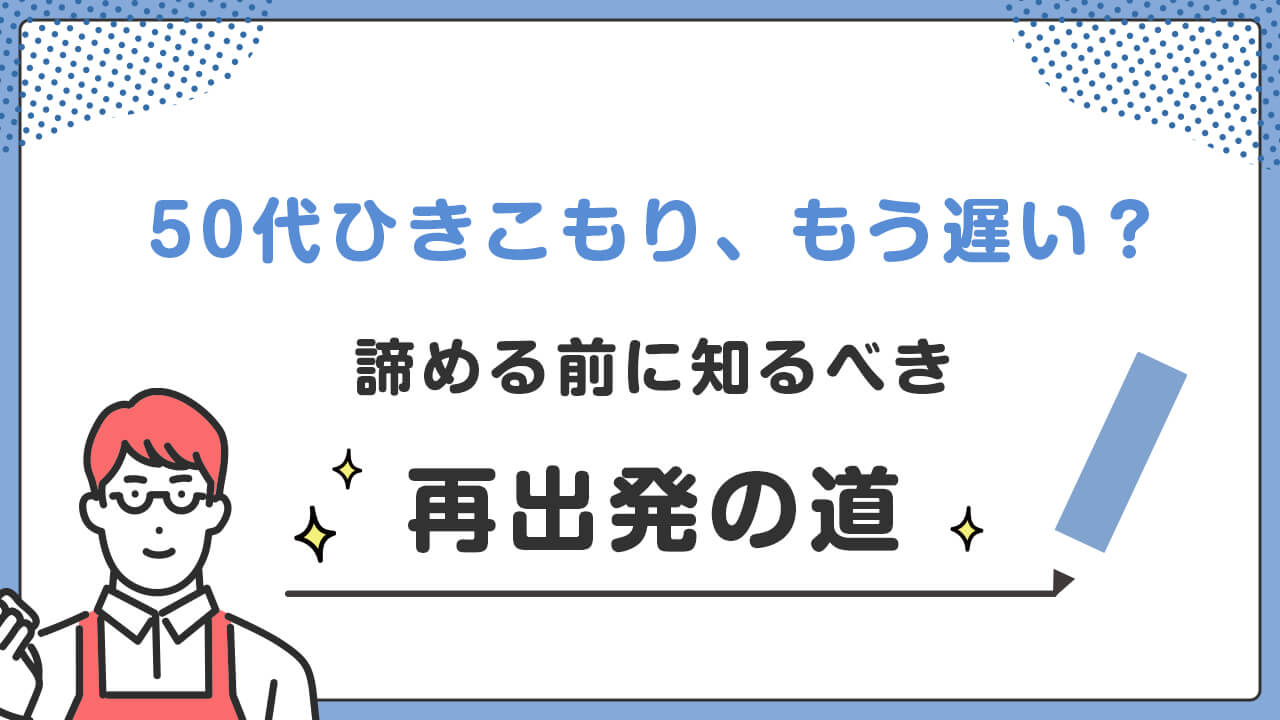「息子が引きこもりで悩んでいる」という悩みを抱えていませんか?
引きこもりになってしまうと、なかなか外に出てくれず、社会復帰ができるのか不安を抱いてしまいますよね。
引きこもりの状態は息子さんの心がデリケートな状態なので、下手な行動を取ってしまうと傷つけてしまい、逆効果になってしまうケースも少なくありません。
そこで札幌市西区にある就労継続支援B型事業所の「ジャバメート」が、引きこもりから社会復帰を目指すための方法について解説していきます。
引きこもりを長期化させてしまいやすい親御さんの行動や社会復帰を目指すために取るべき行動なども解説しているので、息子さんの引きこもりで悩んでいる方は参考にしてみてください。
札幌市西区にある就労継続支援B型事業所「ジャバメート」では、ひきこもりで外出が難しかった方が「社会復帰できた!」という嬉しいお声をたくさんいただいています。お電話またはお問い合わせフォームから「お申込み」いただき、見学・体験ができます。ぜひお気軽にご相談にいらしてください。
目次
まずは知っておきたい「引きこもり」のこと
引きこもりとは、就労や交友などの社会的参加を避けて原則6ヶ月以上にわたって家庭にとどまり続けている状態を指します。
引きこもりの話はデリケートな話になるため、周りの方と話すことがなく、私の息子だけではないかと悩んでいる親御さんも少なくありません。
内閣府が引きこもりの状態に関して調査したところ「15~64歳では50人に1人」が引きこもりになっているという結果でした。
そのため、引きこもり状態になっている方は多く、年齢問わず可能性のある問題としていえます。
引きこもりの状態になってしまうのにはさまざまな理由が考えられるため、引きこもりになりやすい理由を知っておくと刺激してしまうのを避けられるでしょう。
うちの子はなぜ?息子さんが引きこもる、よくある理由

息子さんが引きこもりやすい理由は、6つあります。
- 学校でのつまずき(いじめ、不登校など)
- 就職活動がうまくいかなかった
- 退職したこと
- 人間関係のトラブル
- 病気
- 新型コロナウイルス感染症の影響
それぞれの理由について解説していきます。
学校でのつまずき(いじめ、不登校など)
息子さんが引きこもりになりやすい原因は、いじめや不登校をはじめとした「学校でのつまずき」があげられます。
子どもはささいなことがきっかけでいじめに発展してしまうケースが多く、不当な嫌がらせから学校に行きたくないという気持ちになりやすいです。
また病気などで休みが続いてしまうと、勉強の遅れや久しぶりなので学校で浮いてしまわないかという考えから、不登校になってしまうケースも少なくありません。
学校に執拗に行きたくないという場合は、学校のつまずきが大きな原因になっている可能性が高いです。
就職活動がうまくいかなかった
就職が上手くいかないという理由から引きこもりになってしまう方も少なくありません。
就職活動は大変で、周りの方は成功しているのにもかかわらず、息子さんだけ上手くいかなかった場合は心がくじけてしまいやすいです。
また就職活動で採用面接を何度も繰り返し、なかなかうまくいかなかった数ほど自信がなくなりやすい傾向にあります。
就職活動に苦戦している場合は周りとの差や自信損失から引きこもりになってしまいやすいため、注意するようにしましょう。
退職したこと
退職をしたことによって、引きこもりになってしまう方も多いです。
たとえば「退職後になかなか転職先が決まらず、仕事がなくなった」という場合や、「前職で人間関係の問題があり仕事に行くのがこわい」という可能性があります。
とくに人間関係は難しく、表面的な同調があっても実際には仲が良くないというケースも少なくありません。
人間関係のトラブル
人間関係のトラブルによって、引きこもりになってしまう方も多いです。
たとえば学生時代や職場のいじめ、周りの人とのコミュニケーションが上手く取れないなどの理由から人間関係のトラブルを招き、引きこもりになってしまうケースがあります。
また失恋から人と接するのが苦手になってしまい、引きこもりになってしまう方もいます。
人間関係によるトラブルは心に傷を生みやすく、引きこもりになってしまう可能性があるため注意しましょう。
病気
うつ病や不安障害などのさまざまな病気や障がいが人間関係に影響を与えてしまい、引きこもりになってしまう可能性があります。
ほかにも引きこもりになりやすい精神疾患では、気分障害や脅迫障がい、発達障害や知的障害などがあげられます。
さまざまな要因が人間関係に溝を作ってしまい、引きこもりになってしまう可能性があるため、注意しましょう。気になることがあれば精神科を受診し専門家の意見をきくことをおすすめします。
新型コロナウイルス感染症の影響
新型コロナウイルス感染症の影響から、引きこもりになっている方もいます。
新型コロナウイルス感染症の感染力の高さから、外出する機会が少なくなり、人との接触の少なさからコミュニケーションの低下しやすいです。
コミュニケーションをどのように取ったら良いかわからない点や、家にいるほうが安心できるという点から引きこもりになってしまう方もいます。
また外出が減ることで昼夜が逆転してしまい、不規則な生活から生活リズムが乱れて引きこもりになってしまうというケースも少なくありません。
少しずつ外出をすることで社会復帰を目指せるため、まずは生活リズムを戻すことを意識しましょう。
もしかして私も?引きこもりを長期化させてしまう親御さんの行動
引きこもりを長期化させてしまう親御さんの行動は、以下の4つがあげられます。
- 長期化する仕組み:親が抱え込み、周りに頼れない
- 世間体を気にして相談できない、柔軟に対応できない
- 子どもへの指示や意見が多く、対話が少ない
- 子どもとの共依存状態
それぞれの注意点について解説していきます。
長期化する仕組み:親が抱え込み、周りに頼れない
引きこもりを長期させてしまう行動では、親が抱えてこんでしまい、周りに頼らないという例があげられます。
親が抱え込んでしまうと、息子さんだけでなく誰にも相談できない状態になってしまいやすいです。
カウンセラーや福祉機関などの専門機関や第三者のサポートを受けられないため、問題解決が難しくなり長引いてしまう傾向にあります。
また親自身が精神的に疲労してしまい、息子さんと掛け合う時間が少なくなって長期化する場合も多いです。
家庭内で問題を閉じ込めず、周りの方に助けを求めることが重要になるため、注意しましょう。
世間体を気にして相談できない、柔軟に対応できない
親御さんが「引きこもり=恥ずかしい」という認識を持ってしまい、周りの方に相談できない場合もNG行動です。
世間体を気にしすぎてしまうと、子どもの気持ちや状況に寄り添えていないという状況が生まれてしまいやすいですよ。
親の理想を押し付けると息子さんの心がさらに閉ざされてしまうため、固定概念を捨てて柔軟に受け入れるようにしましょう。
子どもへの指示や意見が多く、対話が少ない
親御さんが指示や意見を出しすぎてしまうと、生きづらい世の中だと感じてしまいやすいため、注意しましょう。
指示や意見ではなく、息子さんとの「対話」が重要で、どのように考えているか聞いていくことが関係づくりで欠かせません。
また指示やアドバイスが多すぎる場合、息子さんが責められていると感じて親に対する信頼感が薄れやすいですよ。
親子の関係に溝ができないように「対話」を重視しましょう。
子どもとの共依存状態
子どもとの共依存状態は、引きこもりを招きやすいため気をつけましょう。
共依存の状態を作ってしまうと、お互いが自立できていない状態になってしまいます。
とくに息子さんが親御さんの期待に応えようと無理してしまい、失敗から挫折・引きこもりへとつながってしまうケースも少なくありません。
自立していくことが大切になるため、息子さんの自主的な経験を大切にして、少しずつ自立していけるように促しましょう。
どうすればいいの?親御さんができる具体的な3つのステップ

親御さんができる具体的な行動では、3つのステップがあげられます。
- まずは親御さんが落ち着くために
- 息子さんとの関わり方を見直す
- 専門家の力を借りる
それぞれのステップについて詳しく解説していきます。
ステップ1:まずは親御さんが落ち着くために
息子さんが引きこもりになって親御さんは心配が絶えないと思いますが、まずは落ち着くようにしましょう。
親御さんが落ち着く方法では、以下の3つがあげられます。
- 休息を取る
- 気分転換をする
- 相談できる人を持つ
それぞれの方法について解説していきます。
休息を取る
息子さんの社会復帰を促したい場合は、まず休息を取るようにしましょう。
親御さんの気持ちは息子さんにも伝わりやすく、焦りから息子さんを不安にさせてしまう可能性がありますよ。
まずは休息を取って親御さんが冷静になれる状態を作りましょう。
気分転換をする
親御さんが落ち着くためにできることとして、気分転換をするのもおすすめです。
たとえば趣味に没頭してみたり、息抜きで旅行に出かけたりしてみるのも良いでしょう。
落ち着いて冷静に状況を分析・向き合うことが重要になるため、不安が募る場合は気分転換をしてみてください。
相談できる人を持つ
息子さんの社会復帰を目指したいときは、周りの方や相談できる相手を持つことも大切です。
相談できる人を持つことにより、第三者の意見を聞くことができますよ。
また誰かに話すことによって、親御さんの気持ちが軽くなりやすいですよね。
自治体の専門機関などを活用し、相談できる人を持つようにしましょう。
ステップ2:息子さんとの関わり方を見直す
親御さんが落ち着くことができたあとは、息子さんとの関わり方を見直すようにしましょう。
息子さんとの関わり方を見直す方法では、以下の3つがあげられます。
- 否定しない、責めない
- 会話のきっかけを作る
- 生活リズムを整える
それぞれの方法について解説していきます。
否定しない、責めない
息子さんと関わりを見直す方法として、否定しない・責めないという点を意識してください。
息子さんを否定・責めてしまうと、関係性が悪化してしまう可能性があります。
心を閉ざしてしまう可能性があるため、息子さんを否定・責めないようにして、まずは相手の話を聞くようにしましょう。
会話のきっかけを作る
息子さんとの関係を構築したい場合は、会話のきっかけを作りましょう。
ささいなことでも問題なく、会話をすることによって徐々に息子さんの心を開くことができます。
日常的なことで問題ないので、会話のきっかけを作っていくようにしましょう。
生活リズムを整える
息子さんとの関係を構築するためには、生活リズムを整えることも大切です。
生活リズムが乱れていると、社会復帰が難しく、引きこもりが長期化してしまう可能性があります。
ただしいきなり生活リズムを整えようとするのではなく、少しずつ朝起きて夜に寝るという状態を作っていくようにすると良いでしょう。
ステップ3:専門家の力を借りる
息子さんとの関係を見直したいときは、専門家の力を借りるようにしましょう。
専門家の力を借りる方法としては、3つの方法があげられます。
- 相談窓口の利用
- 医療機関への相談
- 支援団体との連携
それぞれの方法について解説していきます。
相談窓口の利用
息子さんの悩みを相談したい場合は、子ども家庭支援センターや教育相談施設などを利用しましょう。
たとえば教育相談施設では、学校での様子や学習、親子関係などを相談できます。
子ども家庭支援センターであれば、家庭内の問題や育児の悩みについて相談可能です。
相談窓口を利用することで、第三者の意見を取り入れることができるため、一度利用してみるのも検討してみてください。
医療機関への相談
息子さんの精神的な問題や発達の特性から引きこもりになっている場合は、医療機関に相談するのもおすすめです。
専門家の話を聞くことによって、どのように関わっていけばよいのかわかりますよ。
また息子さんの特性がわかるため、特性に合った過ごし方を提案することができるでしょう。
息子さんが無理なく社会復帰するためには強要しないことが大切なので、精神的な問題や発達に疑問を感じる際には医療機関を受診してみてください。
支援団体との連携
NPO法人や市民団体などと連携して継続的な支援や親同士のネットワークを広げるのもおすすめです。
たとえば発達障害支援センターや自助グループなどを活用すると、専門的な支援が受けられたり、同じ悩みを持つ親同士で経験や情報の共有ができます。
孤立感の解消ができるだけでなく、実体験に基づいた情報の共有ができるため、多くの方におすすめです。
大丈夫!引きこもりから社会へ踏み出すためのステップ
引きこもりから社会へ踏み出すためのステップとして、以下の5つの流れを意識しましょう。
- 現状を知るため精神科や心療内科を受診する
- 生活習慣の改善(睡眠・食事・運動)
- 対人コミュニケーションの練習
- 地域活動支援センターを利用する
- 仕事を探す準備をする
社会復帰を目指す場合は、生活習慣の改善や対人コミュニケーションの練習が必要です。
また地域活動支援センターなどを利用すると、人と触れ合えるため少しずつ社会復帰が可能です。
無理に仕事を探すのではなく「働ける」という準備が整った段階で仕事探しを始めましょう。
引きこもりからの一歩に!就労支援サービスを利用する
いきなり一般企業で働くのではなく、就労支援サービスの利用もおすすめです。
就労支援サービスとは、平成18年4月に施行された障害者自立支援法に基づく就労系障害福祉サービス事業です。
就労継続支援A型とB型事業所があり、A型事業所は雇用契約を結び最低賃金が保証された状態で働きます。
B型事業所は雇用契約を結ばず、通所をして工賃を受け取る働き方で、自分のペースで働ける点が魅力です。
札幌市西区にある就労継続支援B型事業では「ジャバメート」は、引きこもりで外出が難しかったという方も多く通ってくれています。「無理なく少しずつ働くことに慣れる」ことからはじめませんか? 社会復帰を目指したいと考えている方は、ジャバメートに一度ご相談ください。
よくある質問|親御さんの不安を解消します
親御さんが抱えやすい不安では、以下の4つがあげられます。
- いつから「引きこもり」と考えるべき?
- 病院に連れて行くべき?本人が拒否する場合は?
- 親としてやってはいけないことは?
- 引きこもりは治る?家族だけで解決できる?
それぞれの悩みについて解説しているので、気になる質問がある方は確認してみてください。
Q1. いつから「引きこもり」と考えるべき?
引きこもりと認定される期間は、原則6ヶ月からになります。
就労や交友などの社会参加を避けはじめ、家庭に留まり続けている状態は引きこもり予備軍の状態になります。
何かしらの理由から家庭に引きこもっている可能性があるため、無理なく関係を構築して息子さんの傷ついた心が少しでも癒えるような状態を作りましょう。
Q2. 病院に連れて行くべき?本人が拒否する場合は?
本人が拒否している場合は、無理に病院につれていくのは避けましょう。
本人が拒否している場合は、親御さんが医療機関に足を運び、相談してみるのがおすすめです。
また病院ではなく、カウンセリングや訪問支援などを活用する方法もあげられます。
息子さんが拒否する場合は親御さんも不安が募ると思いますが、専門機関と連携を取りながらどのように関わっていくか考えていくのがおすすめですよ。
Q3. 親としてやってはいけないことは?
親としてやっていけない行動としては、以下の例などがあげられます。
- 一方的に正論をぶつける
- 他人と比べる
- 過去の成功体験を語る
- 無理に外に出そうとする
- 責める・否定する
息子さんは心に傷をかかえている状態になるため、責めたり否定したりするのは避けましょう。
また他人と比べたり、自身の過去の成功体験は逆に刺激をしてしまいます。
安心感を与えることが大切になるため、少しずつ会話から始めて心の傷を癒やしてあげるように関わるようにしてみてください。
Q4. 引きこもりは治る?家族だけで解決できる?
息子さんの引きこもりを治すというよりも、本人の意志で少しずつ回復していくのが好ましいです。
また家族だけで解決しようとする方も多いですが、親子間だけでは感情的になりやすく、限界があります。
そのため、第三者からの意見・助言を受け入れたり、支援を受けたりするのがおすすめですよ。
まとめ
息子さんが引きこもりの状態は、社会復帰ができるのか親御さんも不安な状態だと思います。
しかし焦って行動してしまうと逆効果につながってしまうケースが少なくありません。
無理に社会復帰させるのではなく、専門機関や周りの方に相談して第三者の意見や助言を受けるのがおすすめですよ。
息子さんの引きこもりで悩んでいる方は、本記事でご紹介した内容を参考にしてみてください。
まずはジャバメートでお仕事に挑戦してみよう!

ジャバメートは、札幌市西区二十四軒(札幌中央卸売市場向かい)にある、就労継続支援B型事業所です。地下鉄東西線「二十四軒駅」から徒歩8分と、地下鉄で通える便利なアクセス。
- 高収入を目指せる! 頑張り次第で、高い工賃をGET!
- 洗濯スキルがUP! 自分の洗濯物を週1回、仕事として洗えます。
- 自分に合った仕事を選べる! 洗濯、ポスティング、清掃、チラシ折りなど、色々な仕事があります。
- 楽しいイベント盛りだくさん! レクリエーションで、仲間と楽しい時間を過ごせます。
- アットホームな雰囲気!
「働きたいけど、続けられるか不安…」
「体力やメンタル面に自信がない…」
そんな方も、ご安心ください。ジャバメートは、一人ひとりのペースに合わせて、丁寧にサポートします。
普段のジャバメートの様子はInstagramで!
見学はいつでもOK! ご予約いただければ、職員がご案内します。
ご同行も大歓迎です! ご家族や支援者の方と一緒に来ていただけます。
- 交通費として1,000円支給!
- 体験ご希望の方は、昼食をご提供!
お気軽にお問い合わせください。
電話での予約はこちら
見学・体験の申込はこちら!
 札幌 就労継続支援B型事務所
札幌 就労継続支援B型事務所