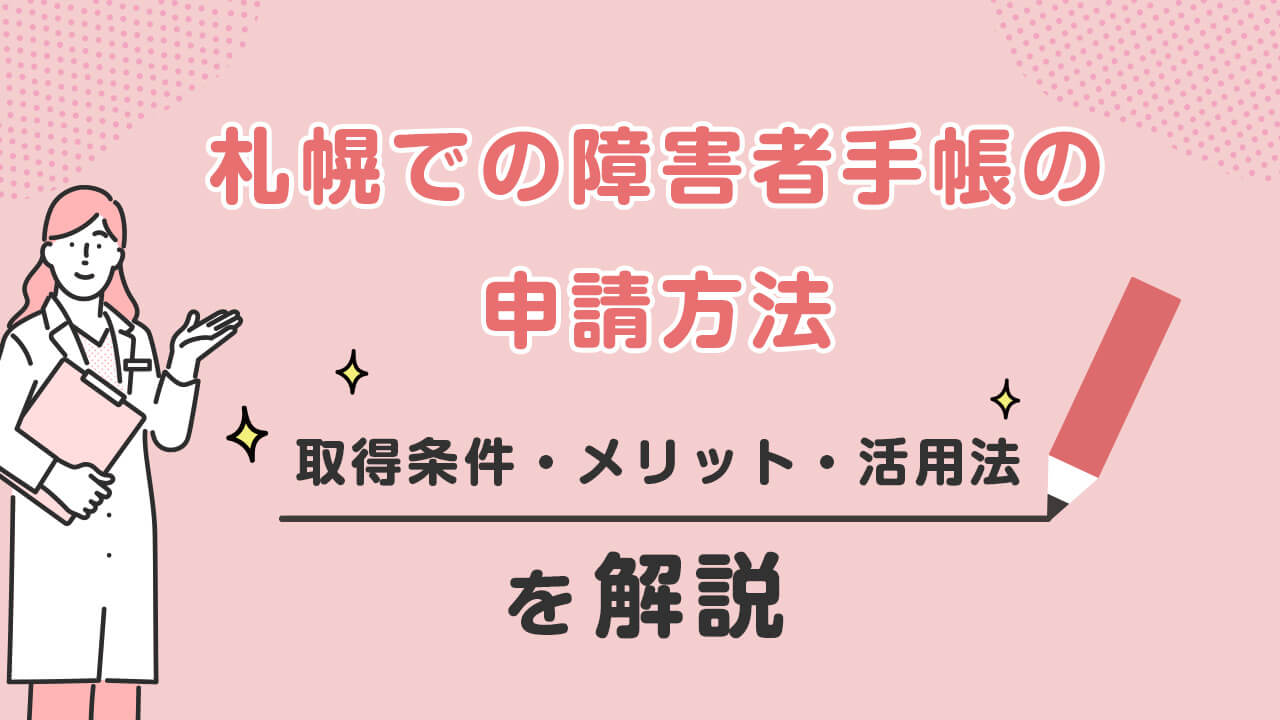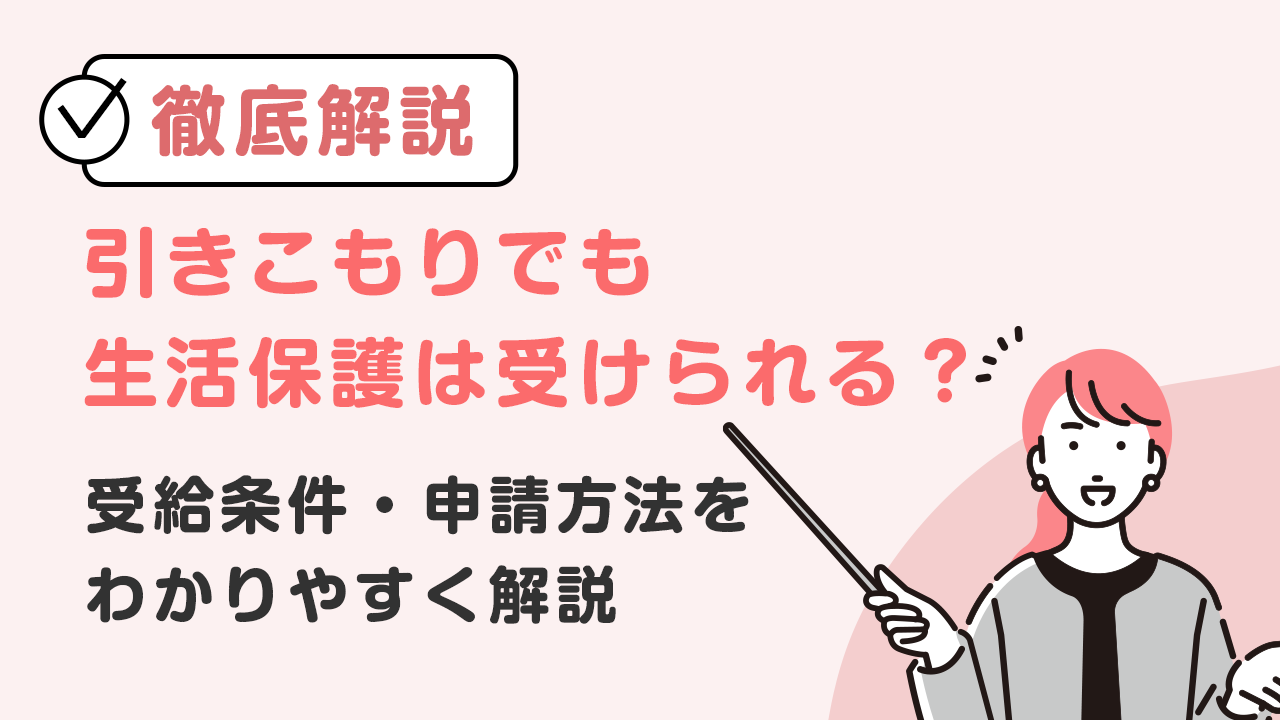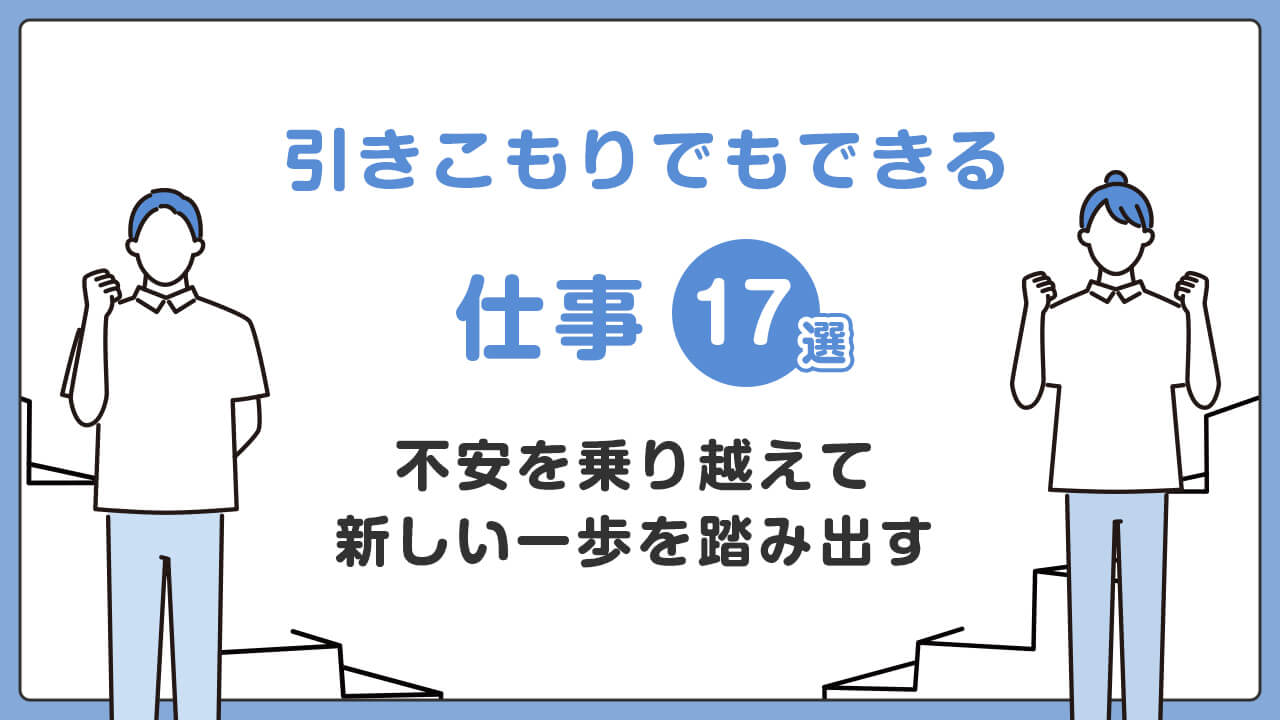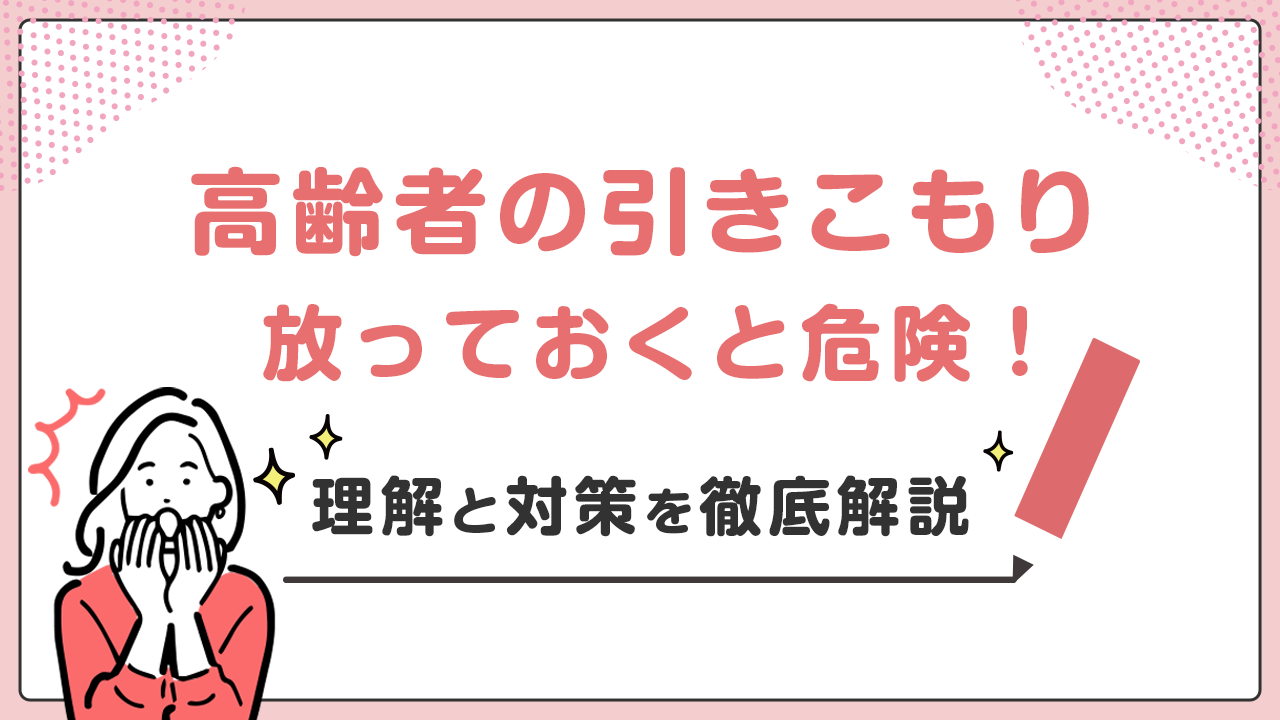
「高齢者の引きこもりは危ないって聞いたけど本当?」
「我が家の親は引きこもりにならないか心配……」
このような悩みを抱えていませんか?
「引きこもり」は若者に多いイメージですが、高齢者の方も少なくありません。
高齢者が引きこもりになる理由は、若い方とはまた異なる理由で、高齢者の場合は深刻な影響が出る可能性があります。
そこで本記事では、高齢者の引きこもりは多いのか、高齢者が引きこもる理由や深刻な影響について解説します。
今日からできるサポート内容までご紹介しているので、参考にしてみてください。
札幌市西区にある就労継続支援B型事業所「ジャバメート」では、65歳以上の方も活躍中です。障がい又は病気がありゆとりをもって働きたい方は、見学・体験ができますので、ぜひお電話にてお気軽にご相談ください。
目次
高齢者の引きこもりってどんな状態?
まずは、高齢者の引きこもりの実態についてご紹介します。
- 「引きこもり」ってどんな状態?高齢者の場合は?
- 増えている?高齢者の引きこもりの現状
- 知っておきたい「8050問題」
それぞれについて解説しているので、参考にしてみてください。
「引きこもり」ってどんな状態?高齢者の場合は?
「引きこもり」は社会的参加を避けて原則6ヶ月以上にわたって家庭に留まり続ける状態を指します。
また高齢者の引きこもりでは、自室にいる場合が多く、自室から出たとしても家から出ないという状態が多い傾向にあります。
そのため、他社と交わる機会が極端に少なく、一人暮らしをしている場合はとくに気づきにくいです。
参照:厚生労働省
増えている?高齢者の引きこもりの現状
厚生労働省が「引きこもり」について調査したところ、初めて引きこもり状態になった方の約7割が40歳以上という結果があります。
また60歳以上では45.2と%という結果で、約2人に1人が60歳以上から引きこもりになったという結果でした。(※1)
さらに40歳~60歳の中高年の引きこもりは61万人を超えており、かなり多いことがわかります。(※2)
2016年9月の段階では54万人だったのに対し、2019年には61万人になっているため、高齢者の引きこもりは増えていることがわかります。
※1参照:厚生労働省
知っておきたい「8050問題」
高齢者の引きこもり問題で「8050問題」も注目されています。
8050問題とは、80代の親が50代の引きこもりの子どもを養っている状態を指します。
高齢であるのにもかかわらず、中高年の引きこもりの世話をしている状態で、社会的な問題となっています。
引きこもりは長期化しやすいため、今後も増加する可能性があり、対策が必要と注目されている状態です。
高齢者の方が引きこもる主な理由

高齢者が引きこもる主な理由は、以下の4つがあげられます。
- 定年退職後の生活の変化
- 体の衰えや病気
- 気分の落ち込み(老人性うつ)
- 人づきあいが減ってしまう
それぞれの理由について解説していくので、参考にしてみてください。
定年退職後の生活の変化
高齢者の引きこもる理由として、定年退職後の生活の変化があげられます。
長年働き続けていたこともあり、中高年の中には生活リズムができている方も少なくありません。
しかし定年退職をすることによって、日々のリズムが崩れたり役割がなくなったことにより気が抜けて引きこもりにつながる方が多いです。
今まで趣味や地域活動に対する意欲も薄れてしまい、外に出る必要性がなくなって引きこもりになってしまいます。
体の衰えや病気
高齢者の引きこもりの理由では、体の衰えや病気もあげられます。
歳を重ねることによって老化が進み、足腰が弱くなって移動が大変という方も少なくありません。
また慢性的な病気や視力・聴力の低下から人との会話や外出に抵抗を感じ、引きこもりになってしまう方は多いです。
気分の落ち込み(老人性うつ)
高齢者の引きこもりでは「老人性うつ」も理由としてあげられます。
老人性うつは高齢者特有のうつ病で、意欲の低下や無関心、睡眠症状などが主な症状です。
日常生活に支障をきたし、興味や喜びなどが損失してしまう状態に陥ります。
そのため、周りの方と会いたくないという気持ちから外に出なくなり、引きこもりになってしまう傾向にあります。
人づきあいが減ってしまう
人付き合いが減ってしまうという点も、高齢者が引きこもりになる理由の一つです。
配偶者や友人、周りの方がなくなってしまい、次第に人と触れ合う機会が減ってしまって引きこもりになる方が少なくありません。
また子どもが独立したことにより、親しい方とも関わる機会が少なくなり、会話の低下から認知機能の低下に結びつき、外出意欲が落ちてしまうケースがあります。
このままでは危険!引きこもりが高齢者に与える深刻な影響
引きこもりが高齢者に与える深刻な影響としては、以下の4つがあげられます。
- 体力低下、筋力低下
- 認知機能の低下
- うつ病、孤独死のリスク
- 社会的な孤立
それぞれの影響について解説していきます。
体力低下、筋力低下
高齢者が引きこもりになってしまうと、歩行や階段などの昇降する機会が少なくなるため、体力や筋力の低下を招きます。
また加齢によって徐々に筋肉が衰えるため、転倒しやすかったり骨折しやすくなったりして、寝たきりの状態になってしまうケースがあります。
そのため、室内にいる場合ではストレッチ・家から出る余裕がある場合は散歩などをするようにしましょう。
認知機能の低下
引きこもりによる影響で、認知機能が低下してしまうケースもあります。
外出や人と触れ合う機会が少ないと、脳を刺激する機会が少なくなってしまうため、認知症を加速させてしまいます。
認知機能の低下を避けたい場合は、脳トレや手芸、日記などを取ることによって脳に刺激を与えることが可能です。
なかでも会話が脳に多くの刺激を与えられるため、認知機能を低下させないためにも誰かと関わるようにするのがおすすめです。
うつ病、孤独死のリスク
うつ病・孤独死は引きこもりによる影響としてあげられます。
長期間一人で過ごしていると、孤独感を強く感じてしまい、自己否定や無力感を生み出してしまうケースも少なくありません。
また体調崩した際に、誰にも気づいてもらえないという状態になってしまうため、定期的な電話や訪問を周りの方や親族に依頼するのが好ましいです。
社会的な孤立
健康状態の悪化や周りの人と関わる機会の低下から、社会的に孤立してしまうケースも少なくありません。
孤立状態になってしまうと、支援の手が届きにくくなり、どんどん助けが求めにくい状態になってしまいます。
地域包括支援センターなど周りの人と関わるような機会をなるべく作り、社会的な孤立を避けるようにしましょう。
もう一人にさせない!今日からできる5つのサポート

高齢者の引きこもり化を避けるために今日からできるサポートとして、以下の5つがあげられます。
- まずは外へ!散歩を習慣にするコツ
- 家の中でもできる!体を動かす工夫
- 地域とつながる!趣味やボランティア
- 専門家を頼る!医療機関への相談
- 相談できる!地域の窓口
それぞれのサポートについて解説していきます。
1. まずは外へ!散歩を習慣にするコツ
高齢者の引きこもり化を避けたい場合は、まず散歩をする習慣を作りましょう。
散歩を習慣化するコツとしては「毎日決まった時間を無理のない距離から始める」というのがポイントです。
また目的をもたせたり、誰かと一緒に歩くという状態を作ると、散歩をする習慣が作りやすいでしょう。
2. 家の中でもできる!体を動かす工夫
筋力低下や体力低下を避けるために、体を動かす工夫をしましょう。
たとえばタオル体操やラジオ体操などをするだけでストレッチになり、筋力や関節の維持ができます。
室内で動くだけでも大きく変わるため、室内でも軽い運動を心がけるようにしてみてください。
3. 地域とつながる!趣味やボランティア
今からできるサポートとして、趣味を作ったりボランティアに参加したりする方法もあげられます。
たとえば高齢者サロンや趣味サークルなどに参加することにより、趣味を楽しみながら周りの方と話せるため、脳を刺激できます。
社会的な孤立を避けられるだけでなく、会話によって脳を刺激できるため、認知力の低下を避けやすいです。
たとえば学校の登下校の見守りや図書館などの読み聞かせなども高齢者が参加しやすいボランティアとしてあげられます。
市町村の広報誌や掲示板などで活動をチェックしてみてください。
札幌市西区にある就労継続支援B型事業所「ジャバメート」では、65歳以上の方も活躍中です。障がい又は病気がありゆとりをもって働きたい方は、見学・体験ができますので、ぜひお電話にてお気軽にご相談ください。
4. 専門家を頼る!医療機関への相談
「元気が湧かない」「食欲がない」「眠れない」などの症状がある場合は、医療機関に相談してみましょう。
第三者の意見やアドバイスを受けることで、早期解決が望めるケースが少なくありません。
また心療内科や精神科であれば高齢者のうつ症状や認知症のチェックも対応してくれるため、状態を知る意味でも医療機関に頼るのはおすすめですよ。
5. 相談できる!地域の窓口
地域の相談窓口を活用すると、社会的孤立や生活貧困状態から避けられる可能性があります。
たとえば市区町村の福祉課に相談すると、生活に関する困りごと全般のサポート・提案をしてもらえます。
また地域包括支援センターであれば介護や福祉などの高齢者の総合相談窓口として機能してくれるため、悩み事に対して丁寧に対応してもらえる可能性が高いです。
相談することによって新しい解決の糸口が見つかる可能性もあるため、地域の相談窓口もチェックしてみましょう。
まとめ
高齢者の引きこもりは、増加・長期化傾向にあります。
なかでも8050問題や少子高齢化による影響から、引きこもり問題が深刻化する可能性が高いと推測されています。
さまざまなサポートを行うだけで社会的孤立を避けられるので、本記事でご紹介した内容を試してみてください。
65歳以上の方も活躍中!ジャバメートで働いてみませんか?

ジャバメートは、札幌市西区二十四軒(札幌中央卸売市場向かい)にある、就労継続支援B型事業所です。地下鉄東西線「二十四軒駅」から徒歩8分と、地下鉄で通える便利なアクセス。
- 高収入を目指せる! 頑張り次第で、高い工賃をGET!
- 洗濯スキルがUP! 自分の洗濯物を週1回、仕事として洗えます。
- 自分に合った仕事を選べる! 洗濯、ポスティング、清掃、チラシ折りなど、色々な仕事があります。
- 楽しいイベント盛りだくさん! レクリエーションで、仲間と楽しい時間を過ごせます。
- アットホームな雰囲気!
「働きたいけど、続けられるか不安…」
「体力やメンタル面に自信がない…」
そんな方も、ご安心ください。ジャバメートは、一人ひとりのペースに合わせて、丁寧にサポートします。
普段のジャバメートの様子はInstagramで!
見学はいつでもOK! ご予約いただければ、職員がご案内します。
ご同行も大歓迎です! ご家族や支援者の方と一緒に来ていただけます。
- 交通費として1,000円支給!
- 体験ご希望の方は、昼食をご提供!
お気軽にお問い合わせください。
電話での予約はこちら
見学・体験の申込はこちら!
 札幌 就労継続支援B型事務所
札幌 就労継続支援B型事務所